1.はじめに 東北地方太平洋側を中心に未曽有の被害をもたらした東日本大震災から丸13年が経過しました。 発災時、宮城県、岩手県では沿岸部が津波による甚大な被害が生じましたが、 現在に至るまで復旧・復興に向けた様々な措置が講じられ、漁業及び関連産業も一定の水準まで回復しています。 折しも、2024年1月1日には能登半島地震が発生し、その後の豪雨災害も相まって、能登地域では現在に至るまで懸命な復旧・復興作業が続いています。 丸1年が経過しましたが、生業たる漁業の再生も期待どおりには進んでいない状況が見られます。 能登半島地震では沿岸部において海底・地盤の隆起、津波等、被害の様相が複雑で、多重的でした。 このことが復旧・復興の困難さを増している要因ともなっています。 ここでは、東日本大震災からの復旧・復興経過をたどり、能登半島地震も含めて今後起こりうる大規模災害を見据え、 「漁業」再生の課題について考察したいと思います。 特に、漁業と流通・加工業等の関連産業との関係性に着目し、両者の復旧・復興の進捗度合が漁業再生に与えた影響に焦点を当てていきます。 2.水産物流通構造と産地市場の機能 皆さんも耳にしたことがあると思いますが、我が国の水産物流通は、 「産地市場」を中核とした産地流通段階と「消費地市場」を中心とした消費地流通段階を経る、いわゆる2段階市場流通が基礎となっています(図-1参照)。基本的に漁業は天然資源の採捕を根幹としており、計画的な生産が困難です。 比較的計画的な生産が可能と考えられる養殖業にあっても、 その生産性は漁場環境(漁場が有する基礎生産力=餌料環境、水温変化等)に大きく左右されますので、工業製品のようには生産できません。 つまり、漁業・養殖業は需要に合わせて生産するのではなく、生産した水産物ありきで、流通させることが求められるプロダクトアウト型の産業と言えます。 日々の水揚げ動向が予測しづらく、品質劣化が早い生鮮水産物を、 迅速に目利き(品質評価)・選別・用途分化し、多様な需要に応じて適正配分する仕組みとして、 産地流通段階を介する2段階市場流通のシステムは有効に機能してきたと評価できます。 加えて、産地市場での取引の一連の過程で適正な価格決定がなされ、代金決済を行う機能は、 1)漁業者の所得を担保すること、 2)消費者へ適正価格で水産物を安定供給すること、 という点で双方に大きなメリットをもたらすものと言えます。 近年は、ICTの普及とともにインターネットを介して個別事業者同士が簡便に需給マッチングを行える時代になってきました。 漁業者や産地買受業者等が消費地の実需者(小売・外食事業者等)や末端消費者と直接取引する流通経路が確立されつつあります。 こうした直接取引の流通形態においても、水揚げするまで何が漁獲されているかわからない水産物の特性を考えれば、 産地流通段階での品質評価・用途分化機能は不可欠です。 結局、直接取引の流通経路においても、産地市場が重要な役割を担っているのです。 このように産地市場は、プロダクトアウト型を基本とする供給サイドのシーズと多様な需要サイドのニーズのマッチングを行う場であり、 水産物の需給の最適化を図る機能を有しているのです。 産地市場を介して水産物が取引される、この日常の経済活動そのものが、需給調整活動と捉えることができ、水産物の用途配分の最適化につながっているのです。 したがって、産地市場の機能が喪失した場合には、漁業生産活動が残存していたとしても、 市場での適正な価格形成ができず、消費地の需要に応じた水産物の円滑かつ適正な供給を維持することが困難になると考えられます。 3.水産物流通からみる漁業再生の課題 東日本大震災では漁港施設や漁場が甚大な被害を受けたことに加え、 漁業関連施設(市場施設・荷捌施設、製氷・貯氷施設、冷凍冷蔵庫等)及び、流通・加工等の関連産業者所有施設も甚大な被害を受けました。 これにより、産地市場を中心とした産地流通機能(商流・物流)そのものが失われたのです。 震災直後の混乱が残る状況下で現場の漁業者の方々にとっては、 1)漁業再建に必要な資金の調達に関する負担が大きいこと、 2)仮に再建したとしても生産物の販売による収入を得られるまでの期間が長く、その間の生活再建がままならない状況が懸念されること、 この2つが大きな懸念材料でした。 これらの課題に対し、漁業者の所得確保支援策や漁業再建のための金融支援措置等国の支援措置は手厚く講じられました。 これらは漁業者の漁業再建マインドの維持に大きく貢献しました。 一方で、流通・加工業等、産地流通を担う関連産業者の復旧・復興は、措置に遅れが生じたことは否めません。 個別民間事業者への補助事業制度の創設に時間がかかったためです。 すでに示したとおり、上記関連産業者は水産物産地流通の中核を成す産業であり、この復旧が産地流通機能の回復に直結するものです。 漁業にとっても漁獲物の換金機能の早期復旧は、漁業再建マインドの維持に大きな効果をもたらすことは間違いありません。 東日本大震災後の漁業再生においても、流通・加工業等の関連産業の早期復旧と足並みを揃えられれば、より効果的であったと思われます。 能登半島地震の復旧・復興にあっても、また、今後想定される我が国の甚大な災害からの復旧・復興にあっても、この教訓を生かす必要があります。 漁業の再生には、関連産業も含めて地域経済の基幹産業たる「水産業」として位置づけ、 発災時の被害軽減、早期復旧、事業継続のための施策を一連の施策として計画しておくことが重要と考えます。 全国の漁業地域の皆さんには、この「事前復興」の考え方を基礎として有事の際の対応策を検討、策定することを提言させていただき、 本稿を閉じたいと思います。 代表 麓貴光
2025年1月15日
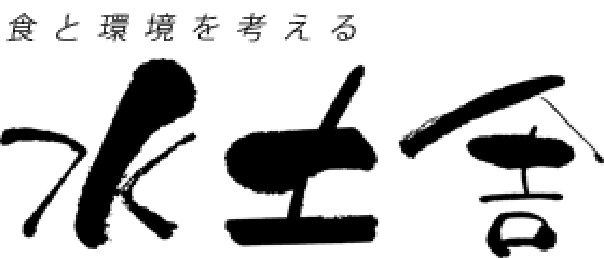

 Top
Top